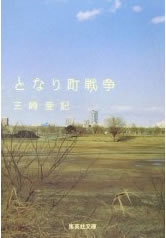 昨日買ってきた、三崎亜記「となり町戦争」を読みました。その感想とかを。
昨日買ってきた、三崎亜記「となり町戦争」を読みました。その感想とかを。
「となり町戦争」は第17回小説すばる新人賞を獲得した作品で、角川ヘラルドから映画化されています(現在公開中)。ヒロインが原田知世という設定がちょっといいかも、って見に行きたくなりました。新宿でやっているみたいですね。
普通の会社員の主人公の住んでいる町と、となり町が「戦争」を始めたと、町の広報に突然発表があり、主人公は「偵察員」として、となり町との戦争に巻き込まれていきます。が、「戦争」が起こっている場面が結局一回も出てこず、公共事業として淡々と見えないところで戦争が遂行され、でも確実に戦死者が出ているという不可解さに主人公は疑問をもちつつ、「となり町戦争推進室」の公務員と淡々と同棲しながら監視業務をこなしていきます。
というストーリー展開で、戦争もの、というわけではありません。おそらく作者は「戦争」という日常を日本の中に描きたかったんじゃないか、と思いました。それが良いとか悪いとかじゃなくて、日本人が遠く感じている戦争がもうちょっと身近だったらどうなんだろう、ってことを書いているじゃないでしょうか。
といっても、別に戦争の意味を問いかけるというほどの主張がある作品でもなく、となり町と戦争するというちょっとありえない日常を丹念に描ていて、そんなところが結構おもしろいです。
さらっと読めるので、暇つぶしにどうぞ。
戦争って、ある意味「公共事業」なんですよね。